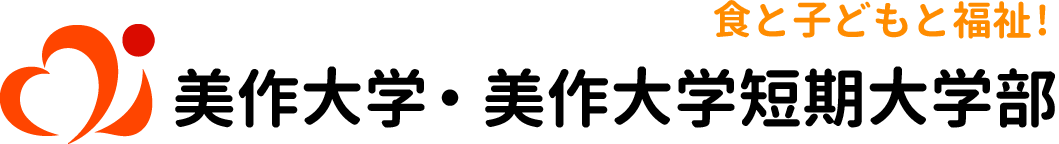食の分野
大学
食物学科
[管理栄養士養成課程]
実習・カリキュラム
管理栄養士養成課程がめざすものは、人の命を支え、健康に貢献したいという心を持ち備えたスペシャリスト。
管理栄養士養成課程では、質の高い技能を修得した管理栄養士の育成とともに、それを活かせる職への就業をめざしています。管理栄養士は、料理センスや調理技術も必要ですが、栄養の面から人の命を支え、“食”を通して、人々をより健康に幸せな生活ができるようサポートを行うスペシャリストです。その人その人の栄養状態が判り、必要とされる栄養をマネジメントできることが求められています。そのため、1年次から4年次まで全ての年次において、管理栄養士としての職業意識が高められるような機会を多く設定しています。また、栄養教育論や給食経営管理論などの実習において、コンピュータを活用した演習・実習を行い、現場の管理栄養士業務に即した実践力を養っています。
病院や福祉施設などでの栄養ケアマネジメントで必要となる臨床栄養学についても詳しく学習するほか、小学校、福祉施設、病院などでの臨地実習を行うなど、学生が管理栄養士としての生きた専門知識や技術を身につけることができるようになっています。国家試験対策として特別演習や集中ゼミも実施します。
全体の流れ
1年次

前期は、管理栄養士の仕事内容や役割、使命を理解(食物学演習)し、また生物や化学など専門教育の準備の科目を履修します。後期に入ると、専門基礎科目がグッと増えます。
2年次

前後期とも、管理栄養士養成課程の専門科目が中心になります。栄養学、栄養教育論、臨床栄養学、公衆栄養学、給食経営管理論など徐々に専門性が高まっていきます。
3年次

2年間学んだ専門教育を総合し、実践的に学ぶ臨地実習(3回)が学校、病院、保健所等で行われます。また教職課程の科目履修が本格化します。
4年次

4年生の生活は、管理栄養士国家試験の準備、卒業研究(選択)、就職活動が中心となります。
国試対策の勉強を通して、専門科目を総合的に復習します(栄養管理総合演習)。
授業紹介
1年次食品学実験
食品学実験では食品素材に含まれる栄養素などの定性、定量分析を行います。分析に必要な基本知識を理解した上で、必要な実験器具の使用方法を修得するとともに、分析機器の取り扱いについても身につけてもらいます。さらに、論理的な化学レポートの書き方を学びます。実験の楽しさがわかる授業です。(納庄康晴/教授)

2年次栄養教育論 実習Ⅰ
本授業では、栄養教育論および各教科で学んだ知識をもとに、対象者の把握のためのアセスメント方法や栄養教育計画から実施、評価までの具体的な方法を修得します。また、集団を対象とした場合の栄養教育計画に基づいた栄養教育を実践し、管理栄養士として現場で活用できる実践力を身につけます。(土海一美/准教授)

2年次給食調理学実習
本授業は、1年次の調理学実習で学んだ少量調理をもとに、大量調理ができるようにするための献立作成や調理方法など、管理栄養士としての給食業務に必要な基礎的マネジメントを修得します。具体的には、利用者の健康を考慮した大量調理ができる献立作成と調理方法を学びます。食材選定や作り方など詳細なレシピを作成し、学生同士で意見交換することで多くの気づきがあります。また、作成したレシピをもとに試作検討を行い、問題点があれば改善して大量調理が可能な献立を作成していきます。(中山真知子/講師)

3年次福祉臨床栄養学実習
本授業では、福祉臨床栄養学で学んだ知識をもとに、要支援者・要介護者・障がい者における栄養ケア・マネジメントについて実践的な能力の習得を目標としています。
具体的には、摂食・嚥下障害に対応した嚥下調整食の献立作成や調理、食事の介助方法などを実習で行います。

カリキュラム
基礎教育分野
一般教養を養い専門的知識を支える基礎教育カリキュラム
(基礎教育分野のうち食物学科基礎科目)
学科基礎科目
| 学年 | 前期 | 後期 |
|---|---|---|
| 1年次 |
|
|
専門教育分野
専門的知識の習得と実践力養成に重点を置いたカリキュラム
専門教育科目講義
| 学年 | 前期 | 後期 |
|---|---|---|
| 1年次 |
|
|
| 2年次 |
|
|
| 3年次 |
|
|
| 4年次 |
|
|
専門教育科目実験・実習・演習
生活科学系及び教職系科目
| 学年 | 前期 | 後期 |
|---|---|---|
| 1年次 |  |
|
| 2年次 |
|
|
| 3年次 |
|
|
| 4年次 |
|
 |
教職関連分野
教員免許状のためのカリキュラム
教職科目
| 学年 | 前期 | 後期 |
|---|---|---|
| 2年次 |
|
|
| 3年次 |
|
|
| 4年次 |
|
|
* 上記のほかに語学等の一般教養科目があります。