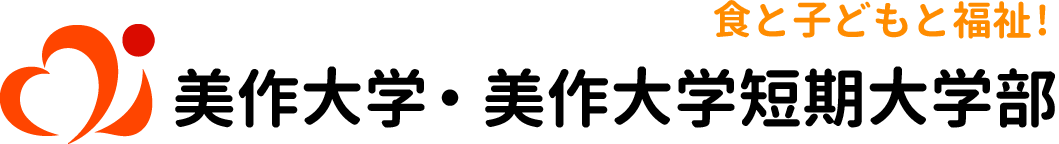学科トピックス
社会福祉学科 武田ゼミ3年 釜ヶ崎・こどもの里 視察研修
2025年09月30日 社会福祉学科
9月19日(金曜)、 社会福祉学科3年生 武田ゼミの学生5名が、大阪市西成区にある釜ヶ崎・こどもの里へ視察研修にいきました。
【午前の部】 釜ヶ崎視察(9:00~13:00)
案内人:NPO法人釜ヶ崎支援機構 理事長 山田實氏
目的
- 釜ヶ崎の街の成り立ちと現状を知る
- 釜ヶ崎が抱える貧困問題について学ぶ
- 釜ヶ崎支援機構の活動目的と事業内容を理解する


活動内容
9:00~10:00 釜ヶ崎の歴史解説
山田氏より、釜ヶ崎が戦後の労働者街として形成され、現在も多くの生活困窮者や路上生活者が暮らしている現状について解説を受けました。かつての労働需要の変化や社会的背景により、地域が抱える課題が深刻化してきた経緯を学びました。
10:00~12:00 街の探索
公園や路上で暮らす人々の姿を実際に目にし、貧困の厳しい現実を体感しました。また、NPO法人釜ヶ崎支援機構が運営するシェルターや生活困窮し自立支援事業、就労支援事業などを見学しました。想像以上に多くの路上生活者が存在すること、また安価な宿泊施設やシェルターがあるにもかかわらず、路上生活を余儀なくされる人がいる実態を知り、参加学生は衝撃を受けました。
12:00~13:00 振り返り
街の様子を振り返り、「行政手続きの遅れが命取りになる可能性」「自己責任論の強さが弱者排除につながる危険性」などを共有しました。支援団体が「できることを先にやる」という姿勢で迅速な支援を実践している点に、学生たちは深い印象を受けました。


【午後の部】 こどもの里視察(13:30~16:00)
講師:認定NPO法人こどもの里 理事長 荘保共子氏
目的
- こどもの里の理念と事業を学ぶ
- 子どもの権利や成長の在り方について理解を深める
- 子どもたちとのふれあいを通して発達の理解を図る


活動内容
荘保理事長より、こどもの里が「子どもの命を大切にする」という理念を掲げ、安心できる居場所、相談できる場、命の大切さを学ぶ教育の場として活動していることを学びました。さらに、保護者支援を通じて虐待防止にもつながっていることを伺いました。
学生たちは「自立」の意味について考えを深めました。これまで「自分で稼ぐ」「一人で生きる」ことが自立と考えていたが、「困ったときに助けを求められる関係を築くこと」「人に頼れること」こそが本当の自立であると知り、大きな気づきを得ました。
訪問の後半には、子どもたちと実際に触れ合う中で、年上の子が年下を助ける姿や、すぐに友達になる柔軟さに接し、子どもの持つ強みや回復力を感じ取りました。
【まとめ】
今回の視察を通じて、学生たちは「貧困」「自立」「子どもの権利」というテーマについて実践的な学びを得ました。釜ヶ崎の厳しい現実と、それに立ち向かう支援活動の重要性を理解するとともに、こどもの里においては「人に頼る力」が自立に不可欠であることを学びました。今後の学習や将来の福祉実践に生かしていきたいと考えています。
【学生の感想について抜粋】
石原 瞳さん(社会福祉学科3年)
- 社会に根強い「働かない=自己責任」という考え方が弱者の排除や差別につながることを学んだ。
- ホームレスの人と直接関わり理解を深める活動の重要性を実感。
- 「こどもの里」での学びから、自立は「一人で生きること」ではなく「頼れる人やコミュニティを持つこと」であると理解した。
- 子どもや人々に「困ったときは頼ってよい」と伝え、支えとなれる存在になりたいと考えた。
山本 彩生さん(社会福祉学科3年)
- 釜ヶ崎の現状を実際に歩くことで、厳しい実態や行政対応の不統一による課題を実感。
- 「こどもの里」で、自立は人に頼りながら生きることだと学び、誤解していた自立の意味を改めた。
- 子どもたちが「自立できない自分」を否定的に捉えてしまう現状を知り、相談できる場や大人の存在の大切さを感じた。
- 今回の経験を今後の学びに生かしていきたいと考えた。
田頭 樹奈さん(社会福祉学科3年)
- 釜ヶ崎は出身地や大学のある地域とは全く異なり、路上生活者や外国人が多く別世界のように感じた。
- シェルターを見学し、厳しい環境を知ると同時に、早期の安定した生活支援の必要性を実感。
- 「こどもの里」で、自立とは「助けを求められる関係性を築くこと」だと学び、教育者を目指す立場からこの考えを伝えたいと感じた。
- 薬物問題についても「裁くのでなく背景を受け止めること」が社会福祉士の役割だと理解した。
- 子ども同士の支え合いの姿に強みを見いだし、夜回り活動への関心も持った。
酒井 彩羽さん(社会福祉学科3年)
- 釜ヶ崎では、行政や地域社会による差別的な扱いを知り、原因や本人の思いに寄り添う必要性を感じた。
- 支援を受けに来る人が遅れる背景に「プライド」や「レッテルを恐れる思い」があることを学び、「支援を受けることは権利である」と伝える重要性を認識。
- 「こどもの里」では、子どもの命を守る場、虐待防止につながる場であることを学んだ。
- 自立は「助けを求められる関係性」を築くことであり、すべての世代に必要なものだと理解。
- 将来は「助けを求められる自立」を支えられる存在になりたいと考えた。
上野 美咲さん(社会福祉学科3年)
- 釜ヶ崎では、行政手続きの遅れが命に直結する問題であることを学んだ。
- 支援団体は「できることを先に行う」実践を通じ、当事者が希望を失わないよう支えていた点に感銘を受けた。
- 「こどもの里」で、自立はお金や能力ではなく「他者に頼れる関係性を持つこと」であると学んだ。
- 子どもは保護の対象であると同時に権利を持つ主体であり、その声を尊重する支援の重要性を理解した。
- 今後は子どもの権利実現に寄与できる支援者を目指したいと考えた。