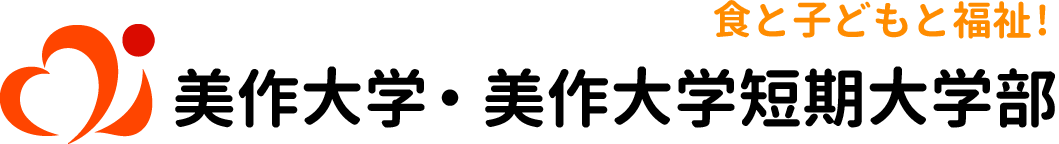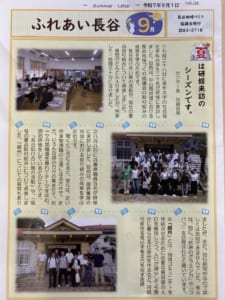学科トピックス
社会福祉学科、佐用町で学ぶ「中山間地福祉のまちづくり」の様子が「ふれあい長谷」に掲載されました
2025年09月11日 社会福祉学科
7月28日(月曜)、社会福祉学科の集中講義「中山間地福祉のまちづくり」(担当:作野広和先生)の一環として、兵庫県佐用町でエクスカーション(実地研修)が行われました。その様子が、長谷地域づくり協議会が発行する「ふれあい長谷」9月号に掲載されました。
<クリックでPDFファイル(614KB)表示>
この集中講義は毎年同時期に開講されており、ソーシャルワーカーを目指す学生たちが、中山間地域に関する理解を深め、福祉と地域との関係性を学ぶ機会となっています。授業では、中山間地域における福祉の実態や役割を把握するとともに、地域課題に主体的に取り組む態度と能力の育成を目的としています。
担当の作野広和先生(島根大学教育学部教授)は、中山間地域の集落研究における第一人者であり、その研究成果を実際のコミュニティづくりやまちづくりに活かし、多くの地域で組織づくりや運営に携わってこられました。
今回のエクスカーションには学生20名が参加。長谷助け合い隊の活動や地域における福祉の重点的な取り組みについて学びました。
学生たちは積極的に質問を重ね、地域の方々との交流を通じて理解を深める充実した時間となりました。
また、この日は長谷地域交流センターのほか、佐用日本語学校での廃校利活用の取り組みや町の現状についての学び、久崎地区センターでの昼食、南光スポーツ公園でのひまわり畑見学、コバコでの協力隊活動や「縮充のまちづくり」に関する意見交換など、多岐にわたる体験を重ねました。
- 学生たちの感想
「住民一人一人の今後の生活が充実したものになるためには、やはり、地域住民が互いに助け合い、協力しながらともに課題解決しに取り組むことが重要だということを改めて感じた。一方で、多様な価値観を持つ人がいる中で、住民自身が相互扶助の意識を持つことはとても難しいとも感じた。」
「目に見える課題だけではなく、『話し相手がいなくてさみしい』などの目に見えない課題を掘り起こし、解決できる共助の大切さを実感した。」
「相手の話をしっかりと聴き、また相手が理解しやすいように説明し、時間をかけて必要性を共有し、信頼関係をつくることの大切さを学ぶことができた。」
学生たちにとって、地域の現状を肌で感じ、住民の方々と直接対話することは、教室の学びを実社会へとつなげる貴重な機会となりました。
本学では、今後も地域と連携した学びを通じて、実践力と地域貢献の精神を備えた人材の育成を進めてまいります。
![]()
![]()
![]()