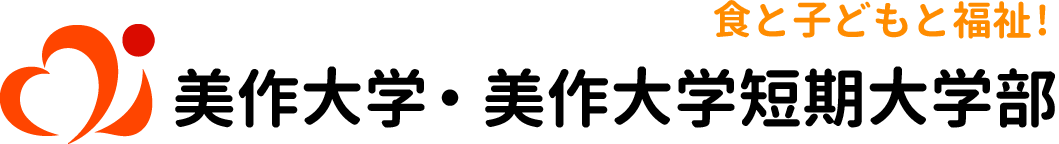学科トピックス
美作市社会福祉協議会 × 松尾ゼミ 地域と学生がつながる ― 子どもの「学び」と「安心」を支える実践 ―
2025年07月24日 社会福祉学科
2025年7月22日(火曜)、美作大学社会福祉学科1年生を対象とした「児童・家庭福祉論」の授業にて、美作市社会福祉協議会(以下、社協)から松本陽さんを講師にお迎えし、子どもの「学び」と「安心」を地域で支える実践について学びました。
講義では、まず地域福祉を担う社協の役割や機能、そして子育て支援の具体的な取り組みについて、実際の事例を交えて紹介していただきました。中でも注目されたのが、「子どもの学習支援・居場所づくり」の活動です。これは、放課後や長期休みに子どもたちが安心して過ごし、学ぶことのできる場を地域全体で支えていこうという取り組みです。松尾ゼミ(4年)もこの活動に参加し、地域の中での実践的な学びを深めています。
- 「安心できる居場所」が育む子どもの成長と、大学生の存在意義
松本陽さんは、講義の中で「地域の中には、様々な困難を抱えながら日々を過ごしている子どもたちがいます。そうした子どもたちにとって、学校や家庭以外に“安心して過ごせる場所”があることはとても大切です。私たちの子どもの学習支援・居場所は、ただ勉強を教えるだけでなく、子どもが“さまざまな体験を通じて成長できる”場所であることを大切にしています。
例えば、一緒にごはんをつくる、一緒に遊ぶ、自然にふれる――そうした体験が、子どもたちの世界を広げるきっかけになります。また、そうした場に大学生が関わってくれることも大きな力になります。居場所に来る子どもたちにとって、大学生は“ちょっと年上のキラキラしたお兄さん・お姉さん”のような存在であり、将来の目標や憧れの姿になることも少なくありません。福祉の専門職を目指す学生が、地域の子どもたちの成長を見守り、一緒に過ごしてくれることは、私たち支援者にとっても本当に心強いパートナーです。」と語られました。
- 学生が現場で培う「人と向き合う姿勢」と自己成長
また、講義の後半では、学生たちが子ども支援に関わる意義について考える時間も設けられました。実際に活動に参加している松尾ゼミ(4年)ゼミ長:合田翔人さんは、「最初は、何を話したらいいのか分からなかったり、子どもとの距離感に悩んだりもしました。でも、“来てくれてありがとう”と子どもが笑顔で言ってくれたとき、自分の関わりが少しでも安心につながっているんだと感じました。子どもたちと関わるなかで、“人と向き合う姿勢”が少しずつ自分の中に育ってきたと感じています。私自身もこの活動を通して、子どもとの関わりの中で自分自身が成長できていると実感しています。ぜひ学生のうちに、こうした体験をしてほしいです」と述べ、現場に飛び込んでこそ得られる学びの価値を共有してくれました。
今回の授業は、福祉の制度や理論を学ぶだけでなく、地域の中で生きる子どもたちの「今」と向き合いながら、自らの学びを現場につなげていく第一歩となりました。
今後も松尾ゼミは、美作市社会福祉協議会と協働して、子どもの育ちと地域の未来を支える取り組みを継続していきます。そして、実践力と共感力を備えた福祉人材の育成に力を注いでいきます。