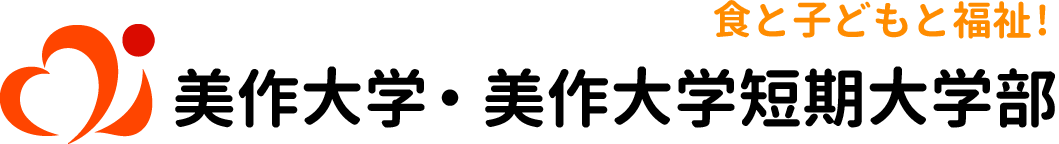学科トピックス
社会福祉学科3年・4年生が社会福祉士学会に参加
2025年07月09日 社会福祉学科
2025年7月5日(土)、第33回日本社会福祉士会全国大会・社会福祉士学会島根大会が開催され、社会福祉学科学生41人と教員7人が参加しました。
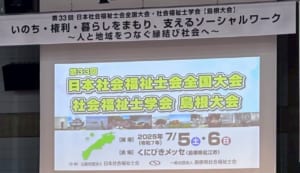
さらに本学会の大会長を社会福祉学科准教授で一般社団法人島根県社会福祉士会会長の田中涼先生が務められました。

社会福祉学科ではソーシャルワーク専門職としての学術的知見を深めるとともに研究的思考を強化するために、希望者には学会への参加機会を設けています。当大会の学会テーマが「いのち・権利・暮らしをまもり、支えるソーシャルワーク〜人と地域をつなぐ縁結び社会へ〜」であり、地域共生社会や権利擁護、包括的支援体制などのプログラムが組まれ、学生にとって学び多き機会になるであろうということで3年生、4年生に呼びかけたところ多くの学生が参加を希望しました。


実行委員の中にも卒業生が複数含まれており、社会福祉士として職能団体においても活躍してくれている姿を見ることができたことも教員陣にとって嬉しい機会となりました。

【学生の感想】
- 上野美咲さん
社会福祉士は真の権利擁護者になりえるかというテーマでの基調講演で髙山直樹先生からの「ソーシャルワーカーは葛藤をすることが必要であり、葛藤しないことは危険である」という言葉が印象的でした。自身の専門知識やスキルでクライエントの問題を解決できるのか、また、新しい知識や技術を習得する必要性を感じながらも、時間や資源が限られている場合などで葛藤が生じた時に、その葛藤に対して解決していけるソーシャルワーカーであれるかが重要だとわかりました。
さらに葛藤は、利用者にとってのより良い支援を模索し、専門職として成長する上で不可欠な過程であると思いました。また、葛藤は決してネガティブな要素ではなく、成長と変化の機会と捉えたり、葛藤を乗り越える経験が困難な状況に直面しても、柔軟に対応し、解決策を見つける力が養われたりするため、ポジティブな要素も持ちうると感じました。
- 馬渕真琴さん
改めてソーシャルワーカーの在り方や、福祉特に地域福祉はどうあるべきなのかを講演を通して学ぶことが出来ました。特に、ソーシャルワーカーも弱みを持ち、それを開示していくことも支援をする上で必要であることが印象に残りました。
- 津田春菜さん
最近の政策動向から社会福祉士に期待されること、実践されてきたことについてのお話を社会福祉のエキスパートから聞くことができ、とても貴重な経験になりました。
「シカタガナイ」という言葉は、政治的な無力感を社会に広めていることになるという言葉が印象的でした。
- 西山明依さん
今回の社会福祉学会島根大会において深い印象を受けたのは、基調講演「社会福祉士は真の権利擁護者になりえるか」でした。我々のものさし(価値観)を考え直し、さらには、クライエントの意思を中心とした、「当事者」の捉え直しによって、関係チームが真に「我が事」として課題に向き合えると理解しました。
そして、友人・ボランティアの弱い紐帯による居場所作りが本人の意思表出を促すために必要であり、権利擁護実現のために重要な役割を持つことを再確認することができました。