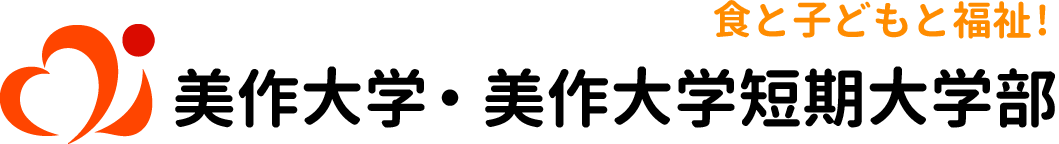Home>学部・大学院>子どもの分野について>児童学科>学科トピックス>未来の先生たちへ:理想の教師像を問い直す 美作第一小学校・時山主幹教諭が学生に与えた気づき
子どもの分野
大学
児童学科
[小学校教員養成コース]
[保育士・幼稚園教員養成コース]
学科トピックス
未来の先生たちへ:理想の教師像を問い直す 美作第一小学校・時山主幹教諭が学生に与えた気づき
2025年07月23日 児童学科
7月23日水曜日、美作大学の4年生を対象とした科目「教職実践演習」において、美作第一小学校の時山祥実主幹教諭より「一学期の放課後学習のふり返り教職を目指す皆さんへ」という特別講義が開催されました。
この講義は、津山市教育委員会と連携した「MIMASAKA METHOD」のプログラムの一環として、教職を目指す学生の教育力向上を目的として実施されたものです。
- プロ意識と自己管理の重要性
講義の中で時山主幹教諭はまず、「プロ意識を持つこと」の重要性を強調しました。経験年数に関わらず、教壇に立つ者は皆「先生」であり、その重みを自覚するよう促しました。
「今の自分をどう変えますか?」という問いかけには、学生たちが互いに意見を交換し、自己変革への意識を高めました。また、日ごろから「見通しを持つこと」の大切さも説かれました。自分一人で進められること、他者と連携が必要なこと、そして「外部の人との連絡」を優先するべきことなど、タスク管理とスケジュール管理の重要性や、「自分が信用されることは学校全体の信用と同じ」と伝え、日頃からの自己管理が学校全体の信頼に繋がることをお話ししました。
- 児童理解と温かい学級経営
児童理解についても深く掘り下げられました。「わかりやすい言葉で話す」「ほめてもらうとうれしい」「わかってもらえる安心感」といった児童の心理に寄り添う姿勢が語られました。「好きな先生・苦手な先生」という問いかけに対し、学生からは「一緒に楽しんでくれた」「認めてくれた」「笑顔」といった肯定的な意見や、「感情がわかりにくい」「気分と感情で支配してくる」といった苦手な先生像が挙げられ、学生自身の経験と重ね合わせながら、児童の視点に立つことの重要性を再認識しました。
学級経営においては、「自分のクラスで授業で何を大切にしたいか、どんなことを頑張ってみたいか」という問いを通して、学生たちに理想の学級像を具体的にイメージさせました。安心安全でメリハリのある、居心地の良い学級づくりが、日頃から学生自身が抱いている「こうだったら居心地よかった」という思いから生まれているのではとの話に学生たちも気づきがあったようでした。
また、「教材研究に終わりはない」とのお話で、日ごろからの自己研鑽や教材研究を行うことの大切さを伝えました。
- 「困っている子」への寄り添い
特に印象的だったのは、気分が乗らない児童への対応についてでした。「だまれ・きもい・しね」といった言葉を使う児童の背景に目を向け、「なぜそのような言葉しか使えないのか」を考えることの重要性が語られました。
児童によって対応が異なること、そして児童を叱る際の「明確なルール」や「見えるところへの掲示」の必要性が強調されました。頭ごなしに叱るのではなく、児童の行動に寄り添い、なぜ今その行動をとっているのか、その背景にある「わからない自分がいや」「わからないことを知られたくない」といった様々な心理に寄り添って対応することに、学生たちも今後の自分を重ねてみているようでした。
そして、「困った子」ではなく「困っている子」という視点を持つことの意義が伝えられました。「困っている子」として、何に困っているのかに焦点を当て、寄り添い、対応していく姿勢、何よりも、「子供が納得して行うこと」が大切であり、教師が良かれと思って指示するのではなく、児童自身が決め、納得したことの方が価値があるという実践的なアドバイスは、学生たちの心に深く響きました。
- 今しかできない経験の積み重ね
時山主幹教諭は最後に、学生に向けて「今しかできない経験をたくさんしよう」とエールを送りました。様々な場所へ出かけ、多様な年齢層の人々と関わり、自分の足で様々なことを体験することの重要性を説きました。
- 学生からの質問と教員の声
講義後には、学生から「学校に居場所がない、居場所と思えない児童にはどう関わればよいか」という実践的な質問が寄せられました。これに対し時山主幹教諭は、すぐに専門家に丸投げするのではなく、「専門家や外部の人と連携を取り、様子を聞き、どう支えていくかを相談し、共に支援していく」という連携の重要性を回答しました。
宮田樹さんからは、教員採用試験対策ばかりに目が向いていた自身の状況を振り返り、「どんな教師になりたいか」という問いを通じて自己を見つめ直すきっかけになったという感謝の言葉が述べられました。宮田さんは、理想の教師像を具体的に想像しながら見通しを持ち、児童との関わり方を考えていくことの必要性を改めて認識したと語り、今回の講義が学生たちにとって大きな学びの場となったことを示しました。