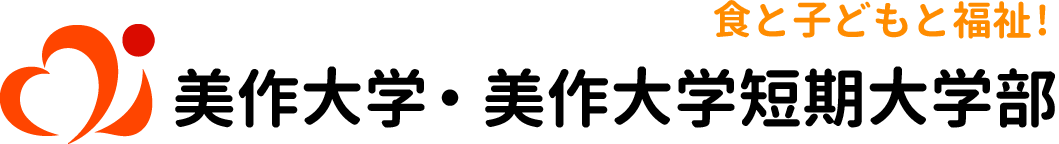Home>学部・大学院>子どもの分野について>児童学科>学科トピックス>「生きのいいさかな」で学ぶ!面磁石の不思議と学級経営のヒント
子どもの分野
大学
児童学科
[小学校教員養成コース]
[保育士・幼稚園教員養成コース]
学科トピックス
「生きのいいさかな」で学ぶ!面磁石の不思議と学級経営のヒント
2025年04月21日 児童学科
児童学科の教員を育成するための科目に「理科概論」があり、この科目に2025年度から新しく薮木二郎先生が着任されました。
初回の授業では「生きのいいさかな」という工作を通じ、面磁石の仕組みを楽しく学びながら、授業の工夫で学級経営が楽しくなるような実践的スキルを身につけることの大切さを伝えました。


この工作では、裏の取っ手を左右に動かすことで、面磁石の力によって表に貼られた魚がピチピチと動きます。この動きは、磁石のS極とN極が引き合ったり反発し合ったりする力を利用しており、子どもたちにとっても楽しい授業内容となります。
しかし、ただ面磁石を貼り合わせるだけでは、魚はピチピチと動きません。生きの良い魚のように動くためには、マグネットシートの極性についての正しい知識が必要です。具体的には、N極とS極がミリ単位で隣り合って配置されていることを利用して、横にずらすことで、それぞれの極が反発し合い、引き合う力が働き、魚が生き生きと動くのです。
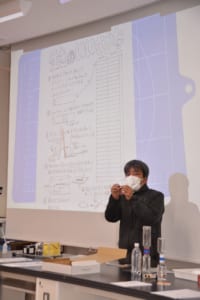
また、面磁石の貼り方にも注意が必要です。90度回して貼り付けると、ピチピチとした動きにはならないため、正しい方向での貼り付けなければなりません。このような経験を通じて、薮木先生は「理科を通じて日常の気づきを子どもたちに伝えることが、学校経営を格段にしやすくする」ということを語ってくださいました。


この授業を通じて、学生たちは理科の楽しさを実感しながら、理科教育の重要性を再認識し、未来の教育者としてのスキルを磨いていくことでしょう。