食の分野
食物学科
[管理栄養士養成課程]
酒税や清酒の製造方法など学び、実際に日本酒を味わいました
2015年11月30日食物学科
11月26日、「お酒に関する講座」が開かれ、酒造りの授業がある食物学科の4年生が、酒税や清酒の製造方法など学び、実際に日本酒を味わいました。この企画は管理栄養士国家試験において頻出する酒税対象や酒類の醸造法の違いなどをより深く理解することを目的に桑守正範教授担当の「管理栄養士特別演習」の一環で行われました。
 広島国税局酒類業調整官の門田正雄さんが、酒税法における酒類の分類や、清酒の製造方法を解説しました。沖縄県出身が多い本学の学生に「泡盛ができたのは、14世紀にタイから琉球王国に製法が伝わったから。焼酎のルーツは泡盛です。」と説明。学生は熱心に耳を傾けていました。
広島国税局酒類業調整官の門田正雄さんが、酒税法における酒類の分類や、清酒の製造方法を解説しました。沖縄県出身が多い本学の学生に「泡盛ができたのは、14世紀にタイから琉球王国に製法が伝わったから。焼酎のルーツは泡盛です。」と説明。学生は熱心に耳を傾けていました。
 続いて、岡山県酒造組合専務理事の佐々木崇光さんが、お酒の味わい方について解説しました。「日本酒は、温度によっての甘みや香りが変化し、様々な味わい方ができます」「岡山の日本酒の特徴は、味のふくらみがあり、香りが芳醇で、すっきりした味のものが多いこと。ぜひ、若い人に飲んでもらいたいです。」と話されました。
続いて、岡山県酒造組合専務理事の佐々木崇光さんが、お酒の味わい方について解説しました。「日本酒は、温度によっての甘みや香りが変化し、様々な味わい方ができます」「岡山の日本酒の特徴は、味のふくらみがあり、香りが芳醇で、すっきりした味のものが多いこと。ぜひ、若い人に飲んでもらいたいです。」と話されました。
続いて、甘みや熟成された香りなどを手掛かりにきき酒に挑戦しました。また、料理に合う日本酒を見つけ、五感でお酒を学ぶために、食事をしながらお酒を味わいました。




◆学生の感想
・日本酒の作り方の違いを詳しく知ることができました。
・利き酒をしてみて、においや香りのちがいがよくわり、日本酒は奥が深いなと思いました。
 広島国税局酒類業調整官の門田正雄さんが、酒税法における酒類の分類や、清酒の製造方法を解説しました。沖縄県出身が多い本学の学生に「泡盛ができたのは、14世紀にタイから琉球王国に製法が伝わったから。焼酎のルーツは泡盛です。」と説明。学生は熱心に耳を傾けていました。
広島国税局酒類業調整官の門田正雄さんが、酒税法における酒類の分類や、清酒の製造方法を解説しました。沖縄県出身が多い本学の学生に「泡盛ができたのは、14世紀にタイから琉球王国に製法が伝わったから。焼酎のルーツは泡盛です。」と説明。学生は熱心に耳を傾けていました。 続いて、岡山県酒造組合専務理事の佐々木崇光さんが、お酒の味わい方について解説しました。「日本酒は、温度によっての甘みや香りが変化し、様々な味わい方ができます」「岡山の日本酒の特徴は、味のふくらみがあり、香りが芳醇で、すっきりした味のものが多いこと。ぜひ、若い人に飲んでもらいたいです。」と話されました。
続いて、岡山県酒造組合専務理事の佐々木崇光さんが、お酒の味わい方について解説しました。「日本酒は、温度によっての甘みや香りが変化し、様々な味わい方ができます」「岡山の日本酒の特徴は、味のふくらみがあり、香りが芳醇で、すっきりした味のものが多いこと。ぜひ、若い人に飲んでもらいたいです。」と話されました。続いて、甘みや熟成された香りなどを手掛かりにきき酒に挑戦しました。また、料理に合う日本酒を見つけ、五感でお酒を学ぶために、食事をしながらお酒を味わいました。




◆学生の感想
・日本酒の作り方の違いを詳しく知ることができました。
・利き酒をしてみて、においや香りのちがいがよくわり、日本酒は奥が深いなと思いました。
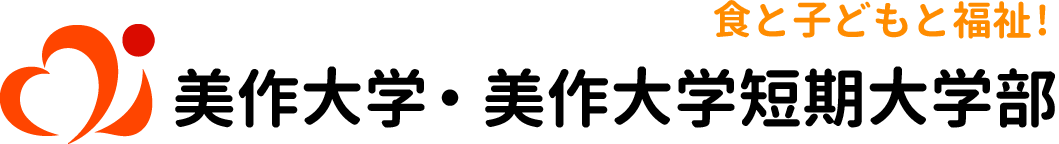

 大学概要
大学概要 CMギャラリー
CMギャラリー 公募情報
公募情報 情報公開
情報公開 生活科学部について
生活科学部について 短期大学部について
短期大学部について 食の分野
食の分野

 子どもの分野
子どもの分野

 福祉の分野
福祉の分野

 大学院
大学院 オープンキャンパス
オープンキャンパス 大学入試
大学入試 短期大学部入試
短期大学部入試 短大 専攻科入試
短大 専攻科入試 大学院入試
大学院入試 編入学入試
編入学入試 試験会場のご案内
試験会場のご案内 入試に関するQ&A
入試に関するQ&A 学費・奨学金
学費・奨学金 過去入試結果
過去入試結果 入試合否検索
入試合否検索 資料請求
資料請求 クラブ・サークル
クラブ・サークル 県人会
県人会 学友会
学友会 キャンパスガイド
キャンパスガイド 年間行事
年間行事 白梅祭
白梅祭 学生の1日
学生の1日 ボランティア活動
ボランティア活動 大学周辺ガイド
大学周辺ガイド 無料野菜市場
無料野菜市場 数字で見るキャンパスライフ
数字で見るキャンパスライフ 生活サポート
生活サポート 学習サポート
学習サポート 障害のある学生へのサポート
障害のある学生へのサポート 学生寮・指定アパート
学生寮・指定アパート 奨学金・学費支援制度
奨学金・学費支援制度 就職サポート
就職サポート 資格取得サポート
資格取得サポート 教職・公務員就職支援
教職・公務員就職支援 就職実績
就職実績 就職に関するQ&A
就職に関するQ&A 求人票ダウンロード
求人票ダウンロード 地域連携
地域連携 企業連携
企業連携 SDGs
SDGs 公開講座
公開講座 出前講座
出前講座 教員一覧
教員一覧 紀要・研究所報
紀要・研究所報 教育・研究機関
教育・研究機関 職員研究助成金研究
職員研究助成金研究 教員免許状更新講習
教員免許状更新講習










