[栄養学科]1年次セミナーで「ヤクルト ウン知育教室」が行われました。(10/2)
2013年10月03日お知らせ
1年次セミナーで「ヤクルト ウン知育教室」が行われました。
平成25年10月2日(水)、本学短期大学部栄養学科の1年生を対象に、「ヤクルト ウン知育(ちいく)教室」が行われました。
 講師としてお招きしたのは、株式会社ヤクルト本社で学術広報・広告を担当されている、管理栄養士 兼 健康運動指導士の山田裕子氏です。
講師としてお招きしたのは、株式会社ヤクルト本社で学術広報・広告を担当されている、管理栄養士 兼 健康運動指導士の山田裕子氏です。「ウン知育教室」とは、ヤクルトさんが実施している健康教室で、“腸内環境をよい状態に保つことが健康で長生きするための秘訣”という考えのもと、腸の健康状態を知る方法のひとつとして、いい便の見分け方などをお話されています。
今回の本学の講義では、便の形や色、匂いからの健康度のチェック方法や、腸内細菌の量・種類・働き、腸内環境を整えるために必要なこと等をお話いただきました。
ヤクルト「ウン知育教室」
“便は健康のバロメーター”と言われますが、いい便は黄色がかった褐色で、バナナのような形、あまり匂わず毎日スルッと出て水に浮き、1日200g〜300gとされているそうです。
 学生が手に持っているのは色、形、重さにおいて理想的な便の模型です。
学生が手に持っているのは色、形、重さにおいて理想的な便の模型です。300gは意外と重く、学生たちはしっかりと色・形・重さをチェックしました。
そしてこの“いい便”は自分の力でデザインすることができ、そのために必要な“3つのウンチ力”について紹介されました。
 1つ目は「ウンチを作るチカラ」
1つ目は「ウンチを作るチカラ」バランスの摂れた食事がいいウンチづくりの基本です。野菜を多く摂り、便をコーディネートしましょう。
2つ目は「ウンチを育てるチカラ」
善玉菌優位の腸内環境を作りましょう。乳酸菌飲料やビフィズス菌飲料を摂ると、腸内に善玉菌が増えてきます。
3つ目は「ウンチを出すチカラ」
腸のまわりの筋肉を鍛えましょう。腸の周りの筋力をつけるための“ヤクルト腸トレ体操”もあります。
これらの“作る・育てる・出すチカラ”がとても大切で、普段の排便の回数により、例えばインフルエンザ等の病気になったときに、重症化する度合いも異なってくるそうです。
腸内環境を良い状態に保つことが、健康で長生きするための秘訣なのです。
そして、腸内細菌には良い働きをする菌と悪い働きをする菌があり、良い働きをする菌が減少すると、腸内環境のバランスを崩します。
良い働きをする菌を優勢に保つために有効なのが、乳酸菌やビフィズス菌を摂取することです。
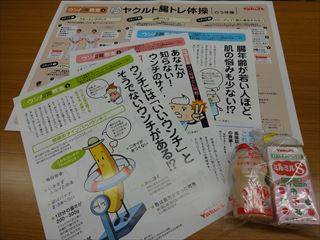 今はさまざまな乳酸菌飲料やビフィズス菌飲料がありますが、今回は“ヤクルト400”と“ミルミルS”が全員に配布され、それらを味わいながらそれぞれの菌の働きについてお話いただきました。
今はさまざまな乳酸菌飲料やビフィズス菌飲料がありますが、今回は“ヤクルト400”と“ミルミルS”が全員に配布され、それらを味わいながらそれぞれの菌の働きについてお話いただきました。(ちなみに私たちのお腹の中にいる腸内細菌は、数百種類100兆個、菌を横並びにすると、地球を2周半する長さになるそうです。)
講義を終え、出席した栄養学科1年の河井さん(岡山県美作高校出身)は、「健康な身体を守っていくためにも、3つのウンチ力をパワーアップしていこうと思いました。」と話しました。
将来栄養士として人々の健康維持・増進に関わっていく栄養学科の学生にとって、今回の「ウン知育教室」は、自分の健康のみならず、周りのすべての人の健康維持に必要な腸内環境について具体的に学ぶことができ、大変有意義な時間となりました。
:-)
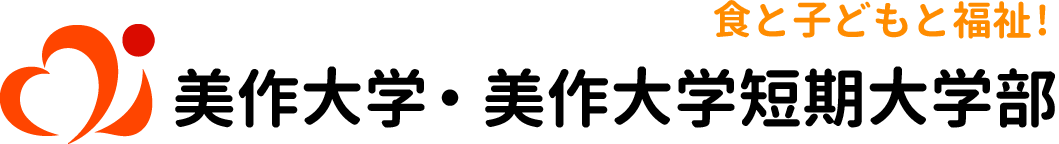

 大学概要
大学概要 CMギャラリー
CMギャラリー 公募情報
公募情報 情報公開
情報公開 生活科学部について
生活科学部について 短期大学部について
短期大学部について 食の分野
食の分野

 子どもの分野
子どもの分野

 福祉の分野
福祉の分野

 大学院
大学院 オープンキャンパス
オープンキャンパス 大学入試
大学入試 短期大学部入試
短期大学部入試 短大 専攻科入試
短大 専攻科入試 大学院入試
大学院入試 編入学入試
編入学入試 試験会場のご案内
試験会場のご案内 入試に関するQ&A
入試に関するQ&A 学費・奨学金
学費・奨学金 過去入試結果
過去入試結果 入試合否検索
入試合否検索 資料請求
資料請求 クラブ・サークル
クラブ・サークル 県人会
県人会 学友会
学友会 キャンパスガイド
キャンパスガイド 年間行事
年間行事 白梅祭
白梅祭 学生の1日
学生の1日 ボランティア活動
ボランティア活動 大学周辺ガイド
大学周辺ガイド 無料野菜市場
無料野菜市場 数字で見るキャンパスライフ
数字で見るキャンパスライフ 生活サポート
生活サポート 学習サポート
学習サポート 障害のある学生へのサポート
障害のある学生へのサポート 学生寮・指定アパート
学生寮・指定アパート 奨学金・学費支援制度
奨学金・学費支援制度 就職サポート
就職サポート 資格取得サポート
資格取得サポート 教職・公務員就職支援
教職・公務員就職支援 就職実績
就職実績 就職に関するQ&A
就職に関するQ&A 求人票ダウンロード
求人票ダウンロード 地域連携
地域連携 企業連携
企業連携 SDGs
SDGs 公開講座
公開講座 出前講座
出前講座 教員一覧
教員一覧 紀要・研究所報
紀要・研究所報 教育・研究機関
教育・研究機関 職員研究助成金研究
職員研究助成金研究 教員免許状更新講習
教員免許状更新講習










